花言葉の歴史
- Kazushige Maeda
- 2025年7月23日
- 読了時間: 3分
花言葉とは何か?
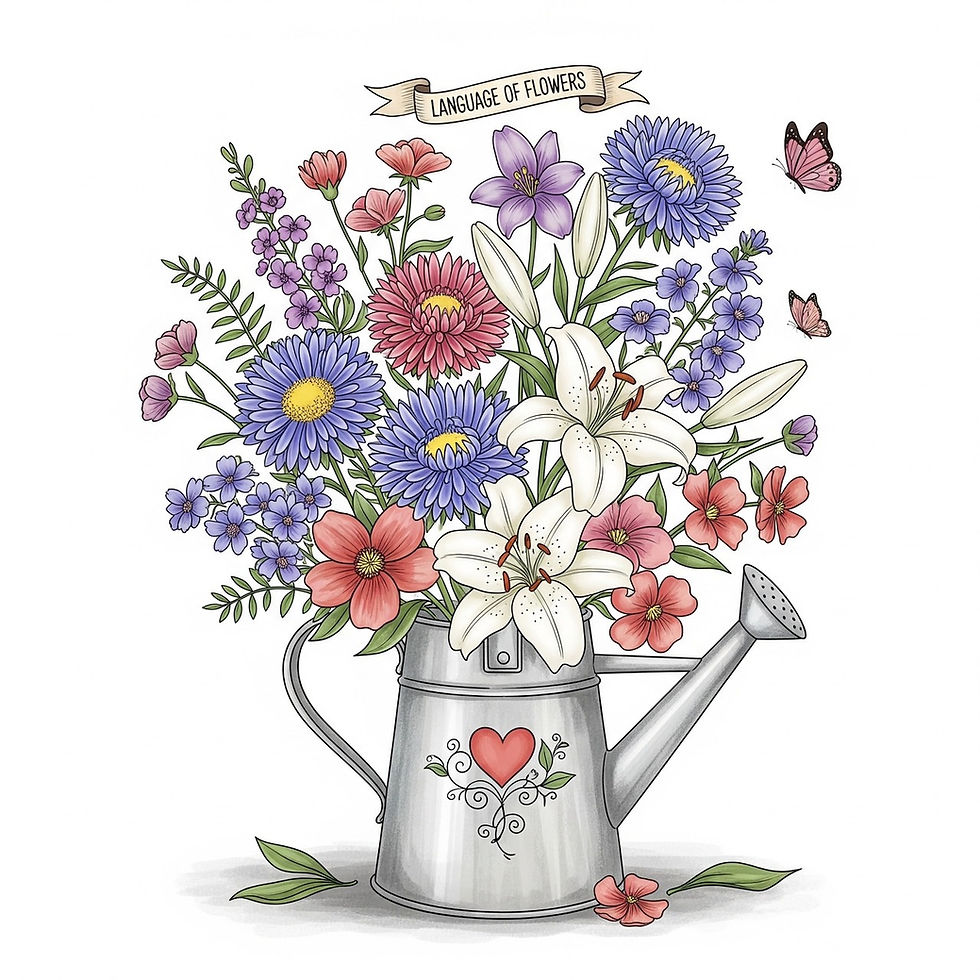
花言葉(フラワー・ランゲージ)は、花に特定の意味や感情を込めて表現する文化です。
「バラは愛」「ひまわりは憧れ」
といったように、花を通して言葉では
伝えにくい思いや願いを表現する手段として広く親しまれてきました。
では、この花と言葉の結びつきは、いつどのように始まったのでしょうか?
古代の花と象徴の始まり
花に象徴的な意味が与えられる
という文化は、実は非常に古く、
古代ギリシャやローマ時代にはすでに存在していました。
たとえばギリシャ神話では、アネモネの花は愛と死の象徴とされ、
バラは女神アフロディーテに捧げられる愛の花でした。
古代エジプトでも、蓮の花が再生や太陽の象徴とされ、
神殿や墓の装飾に用いられています。
これらはまだ「花言葉」という形ではないものの、
花に意味を見出す文化の源流といえるでしょう。
花言葉としての確立:オスマン帝国からヨーロッパへ
現在のような「花に意味を与えて感情を伝える」という花言葉のスタイルは、
18世紀のオスマン帝国(現トルコ)に由来するといわれています。
トルコでは「セラム(Selam)」という秘密の手紙文化があり、
特定の花や果物を組み合わせて意味を伝える暗号のような遊びがありました。
このセラム文化は、外交官や旅行者によってヨーロッパに伝えられ、
特に19世紀のヴィクトリア朝時代のイギリスで花言葉として発展しました。
言葉にしづらい恋心や感謝を、花に託して伝える方法として、
当時の貴族や上流階級の女性たちの間で流行したのです。
日本の花言葉:明治期からの西洋文化の影響
日本に花言葉が紹介されたのは明治時代。
西洋文化の流入とともに、花にも意味があるという考え方が入ってきました。
しかし、日本にはもともと「季節の花を愛でる文化」や、
「和歌や俳句に花を詠む」という感性があり、
花を通して感情を表現するという面では似た土壌がありました。
たとえば、桜は「儚さ」、菊は「高貴」や「不老長寿」といった意味をもって、
日本独自の象徴性を形成してきました。
やがて日本でも花言葉の辞典や図鑑が作られ、
独自の意味づけが加わっていきました。
現代の花言葉とその役割
現代では、花言葉はギフトや冠婚葬祭、園芸、恋愛表現など、
さまざまな場面で活用されています。
たとえば、誕生日に「あなたを幸せにします」という意味のガーベラを贈ったり、
プロポーズに「情熱の赤いバラ」を選んだりするなど、
想いを託す手段として広く浸透しています。
ただし、花言葉は国や文化によって意味が異なる場合もあります。
例えば、ヨーロッパでは白い百合は「純潔」を意味しますが、
東アジアでは「死」を連想させることもあります。
そのため、花を贈る際は、相手の文化や価値観にも配慮することが大切です。
おわりに
花言葉は、時代や地域によって変化しながらも、人々が花に思いを託してきた証です。
目に見えない気持ちを、自然の美しさとともに伝えるこの文化は、
これからも多くの人の心に寄り添っていくでしょう。




コメント