ドライフラワーの起源はいつ?
- Kazushige Maeda
- 2025年7月22日
- 読了時間: 3分

ドライフラワーとは?
ドライフラワーとは、生花を乾燥させて保存性を高めた花のこと。
自然な美しさを保ちながら長期間楽しめるため、インテリアやギフト、
仏花など幅広く利用されています。
現代では、ナチュラル志向のインテリアや
ウェディングブーケとして人気がありますが、実はその歴史は非常に古く、
多くの文化に根ざしています。
古代から始まるドライフラワーの歴史
エジプト文明:死後の世界への贈り物
ドライフラワーの起源は、紀元前4000年ごろの古代エジプトまでさかのぼります。
王や貴族たちの墓からは、ミイラと一緒に花やハーブが発見されており、
それらは死後の世界でも花の香りと美しさを楽しめるようにと供えられたものでした。
保存性を高めるために乾燥された花は、今日のドライフラワーの原型といえます。
古代ギリシャ・ローマ:薬草と香りの文化
古代ギリシャやローマでは、花だけでなくハーブや薬草も乾燥させて保存し、
治療や香料として使われていました。
特にラベンダーやローズマリーなどは、室内の芳香や虫除け、
さらには神事にも利用されていた記録があり、
ここでもドライフラワー的な使い方が見られます。
中世ヨーロッパ:芸術と信仰の融合
中世ヨーロッパでは、
ドライフラワーは宗教的な装飾や民間療法として使われるようになりました。
修道院では薬草とともに乾燥させた花が記録されており、
またキリスト教の祭壇装飾としても重宝されていました。
さらに、香りを閉じ込めた「ポプリ」として室内を彩る風習も始まりました。
また、17世紀のイギリスやフランスでは、
貴族階級の間で「押し花アート」や「花の装飾画」が流行し、
ドライフラワーは芸術表現の一部として発展しました。
日本におけるドライフラワー文化
日本では、仏花や薬草の保存といった形で、昔から乾燥させた植物が使われてきました。
しかし、インテリアや装飾としてのドライフラワー文化が広がりを見せたのは、
明治時代以降、西洋文化の流入とともに始まります。
近年では、ナチュラル志向の高まりとともに再注目され、
手作りのアレンジやスワッグなども人気となっています。
現代:サステナブルな美の象徴へ
現在のドライフラワーは、美しさと実用性、
そしてサステナビリティの象徴として再評価されています。
生花に比べて廃棄が少なく、環境への負荷も低いため、
エコフレンドリーな選択として注目されるようになりました。
また、色や形の変化を「味わい」として楽しむライフスタイルが広がっています。
おわりに
ドライフラワーは単なる装飾品ではなく、
古代の宗教や医学、芸術や信仰の中で育まれてきた奥深い文化遺産です。
過去と現在をつなぎ、人々の暮らしに寄り添ってきたその存在は、
これからも新しい形で愛され続けていくでしょう。


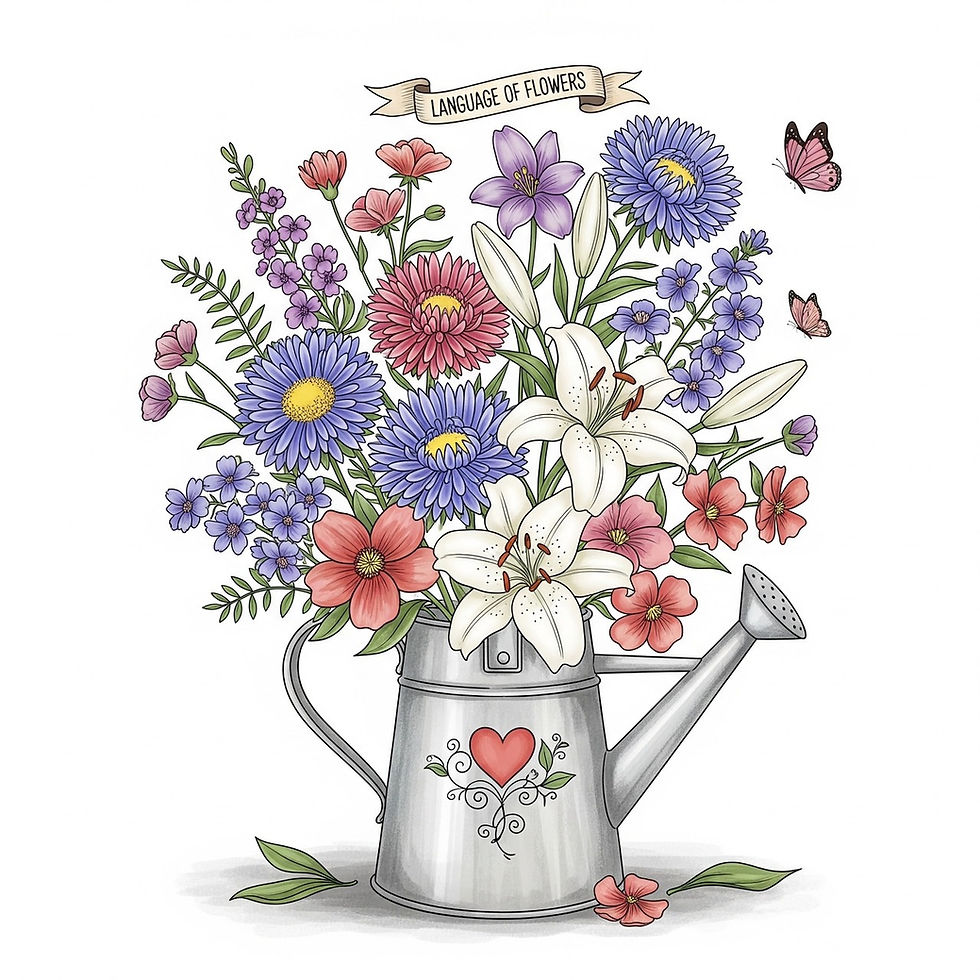

コメント