墓花を供えはじめたのはいつから?
- Kazushige Maeda
- 2025年7月21日
- 読了時間: 3分
6万年前のネアンデルタール人

墓に花を供える最古の例として、
考古学的考察では
約6万年前のネアンデルタール人のものではないかとされていました。
イラク北部にあるシャニダール洞窟遺跡の発掘調査で、墓の周囲からムスカリという花の花粉が発見されました。
これは、ネアンデルタール人が死者に花を手向けた最初の事例と考えられ、
このムスカリは「最古の埋葬花」と呼ばれていました。
しかし、改めて堆積物中に保存されていた花粉の再調査を行ったところ、
花粉の粒の大きさ、形状、表面の質感は、植物の種類によって異なることが判明。
さまざまな種類の花のものであり、
同一の時期に咲く花のものではないことが明らかになりました。
これは、埋葬時などの限られた期間に収集されたのではなく、
長期間にわたって集められたことを示唆しています。
したがって、花を供えていたのではないかという確信を持てなくなってしまいました。
では、現在のところ史上初の供花はいつごろ行われたのでしょうか?
約1万2000年前
イスラエル北部のカルメル山の洞窟で発見された墓地からは、
ミントやセージなどの花や茎の痕跡が見つかっています。
花で飾られた墓は4基並び、そのうち1つには2遺体が埋葬されていました。
ナトゥーフ文化の時代に生きた人々だったようです。
これらの発見は、人類が非常に古い時代から、死者を悼み、敬意を表すために植物を利用していたことを示唆しています。
当初は、遺体の腐敗を遅らせたり、
動物を遠ざけたりするための薬効成分の利用という側面もあったかもしれません。
やがては故人への思いや祈りを込めて花を供えるという、
象徴的な意味合いが強くなっていったと考えられます。
日本ではいつ頃から?
日本における墓への供花の習慣は、
主に仏教の伝来と普及とともに広まったと考えられます。
仏教と花の結びつき
仏教では、花は仏様の慈悲や忍耐、そして清浄さを象徴するものとされています。
仏教が日本に伝来したのは6世紀中頃(538年)とされており、
この仏教の教えと共に、供花(仏様への花のお供え)の文化も
伝わったと考えられます。
仏具の「三具足」(香炉、ろうそく、花立て)にも
花が欠かせないものとされています。
具体的な墓への供花の習慣:
古くから、日本でも葬送儀礼において花が用いられてきたと考えられます。
ただし、庶民の間でお墓を建てる習慣が浸透したのは、
江戸時代初期の寺請制度(約400年前)以降と言われています。
この頃から、より一般的な習慣として墓への供花も広まっていった可能性があります。
特に菊が仏花として広く用いられるようになったのは、
比較的新しく、第二次世界大戦後に年中栽培されるようになってからという説もあります。それまでは、四季折々の野の花が供えられていたと考えられています。
結論として、「墓に花を供える」という行為は、仏教の伝来とともにその思想的な背景が形作られ、具体的な習慣として庶民の間で広まったのは、お墓が普及した江戸時代以降と考えられます。 しかし、明確な「いつから」という記録は残っておらず、時代とともに徐々に定着していった習慣と言えるでしょう。


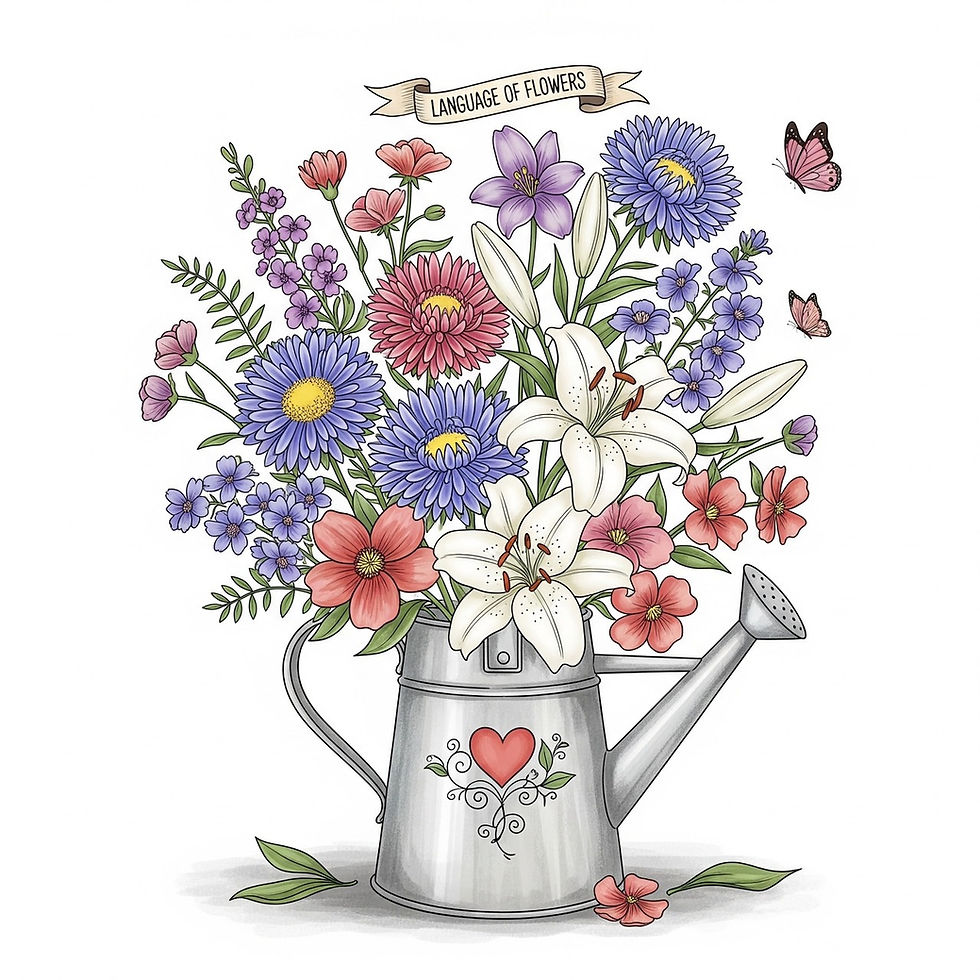

コメント