戦国武将はなぜ花を愛したか
- Kazushige Maeda
- 2025年7月15日
- 読了時間: 3分
家紋には、古来日本からある花を採用しているものがあります。
長宗我部家、宇喜多家の片喰紋
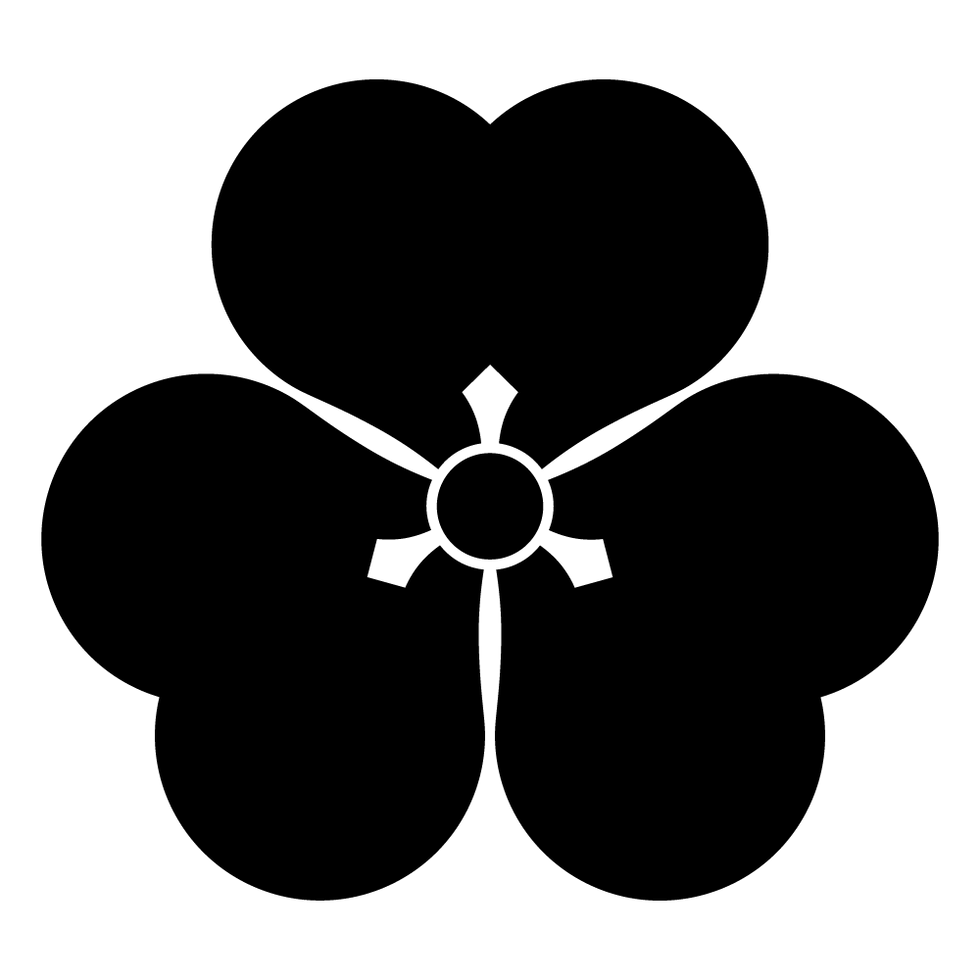
長宗我部氏の祖先が天皇から領地を賜る際、その盃にカタバミの葉が一つ浮いていたことから、これを縁起が良いものとして家紋にしたという逸話です。
これは江戸時代の軍記物「元親記」にも
記されています。
宇喜多氏の家紋は、通常の片喰紋に加えて、葉の間から「剣」を配した「剣片喰」という形がよく知られています。この「剣」は、古来より尚武のシンボルとされてきた諸刃の直刀を意味し、武家としての力強さや、戦での武功を象徴する意味合いが込められていると考えられます。
土岐家の桔梗紋
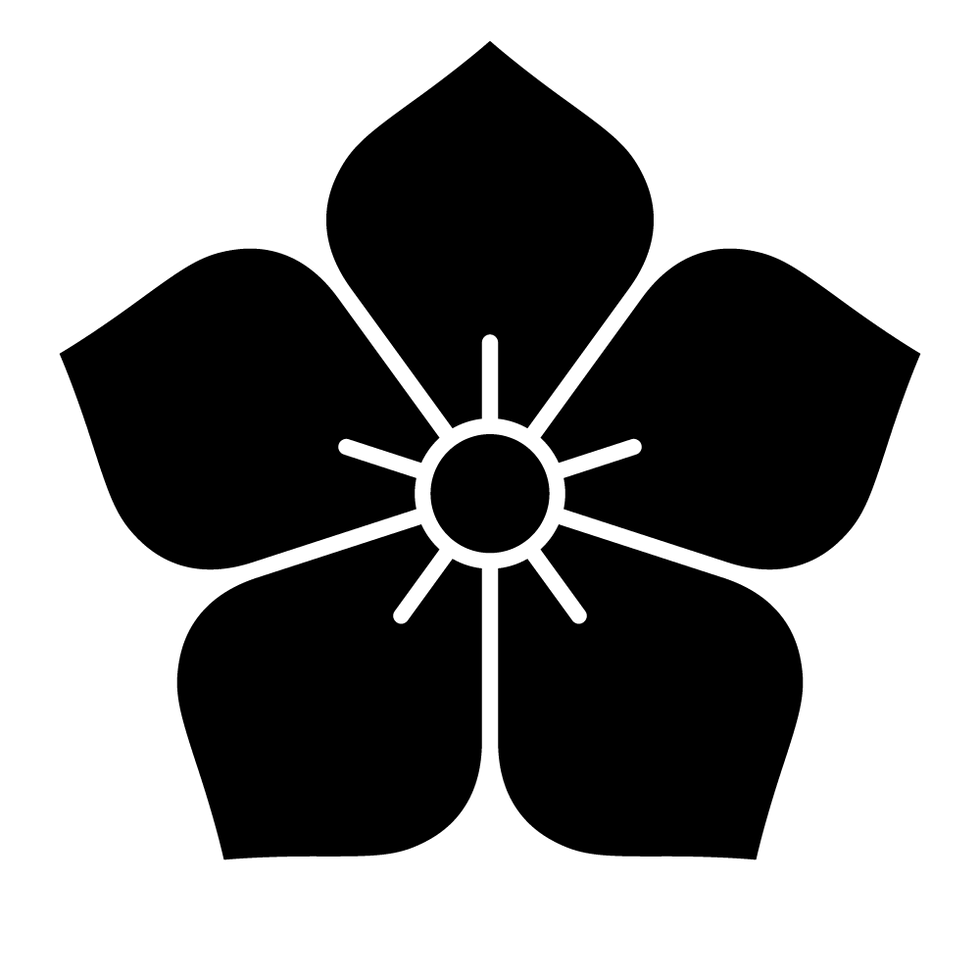
土岐氏は、美濃国(現在の岐阜県南部)を本拠とした清和源氏の有力な武家で、室町時代には美濃守護を務めるなど、大きな勢力を持っていました。桔梗紋は、この土岐氏の代表的な家紋として知られています。
土岐氏の桔梗紋は、特に水色桔梗として有名です。これは、当時の家紋がほとんど単色である中で、水色という特定の色を用いていた非常に珍しい家紋でした。これは、土岐一族にとって水色が重要なイメージカラーであったためとも考えられています。
徳川家葵の御紋
賀茂神社との繋がり

徳川家の前身である松平氏が、本拠地三河(現在の愛知県東部)の賀茂神社の氏子であったことに由来すると言われています。京都にある上賀茂神社と下鴨神社(いずれも賀茂神社)の神紋は「二葉葵(ふたばあおい)」と呼ばれる葵紋であり、松平氏はこの賀茂神社の信仰と縁が深かったため、葵紋を用いるようになりました。
神聖な植物
葵(特にフタバアオイ)は、古くから神聖な植物として扱われてきました。特に京都の賀茂神社の例祭である「葵祭」では、葵の葉が飾りに用いられるなど、神事と密接に関わっていました。この神聖な植物を家紋とすることで、家の権威を高める意図があったと考えられます。
もちろん、花や草木以外の家紋も多くありますので、上記は一例に過ぎません。
しかしながら、史上の戦国武将にとって花は特別な意味を持って愛すべきものであったように思います。
精神性との合致
質実剛健の象徴
戦国武将が家紋にする花は、華やかさはないものの
厳しい環境でも力強く生き抜く生命力を持っているものがよく選ばれています。
これは、武士が求める質実剛健さや、
どんな困難にも耐え抜く精神と通じるものがあったのかもしれません。
地味なものへの美意識
欧米の紋章が鳥獣を使うのに対し、日本の家紋の多くが植物、しかも比較的地味なものが好まれたという指摘もあります。そこには、派手さよりも本質的な強さや生命力に価値を見出す武士の美意識が込められていた可能性があります。
茶の湯との関連
戦国時代後期には、武将たちの間で茶の湯が盛んになります。
茶の湯は「わび・さび」といった質素で静寂な美を重んじる文化であり、
野草が持つ素朴さや自然のままの姿が、その美意識と共鳴したのではないでしょうか。
こだわりの花
徳川家康は、観葉植物の「万年青(おもと)」を好み、
縁起の良い植物として珍重したことは有名です。
また、織田信長がトウモロコシの「絹糸」の美しさを愛でたという話も残っています。
これらは、単なる実用性だけでなく、個人の趣向や美意識が反映されたものと言えるでしょう。
戦国武将が野草を愛した理由は武士としての生き方や精神性、さらには当時の文化的な美意識が複合的に絡み合っていたと考えられます。


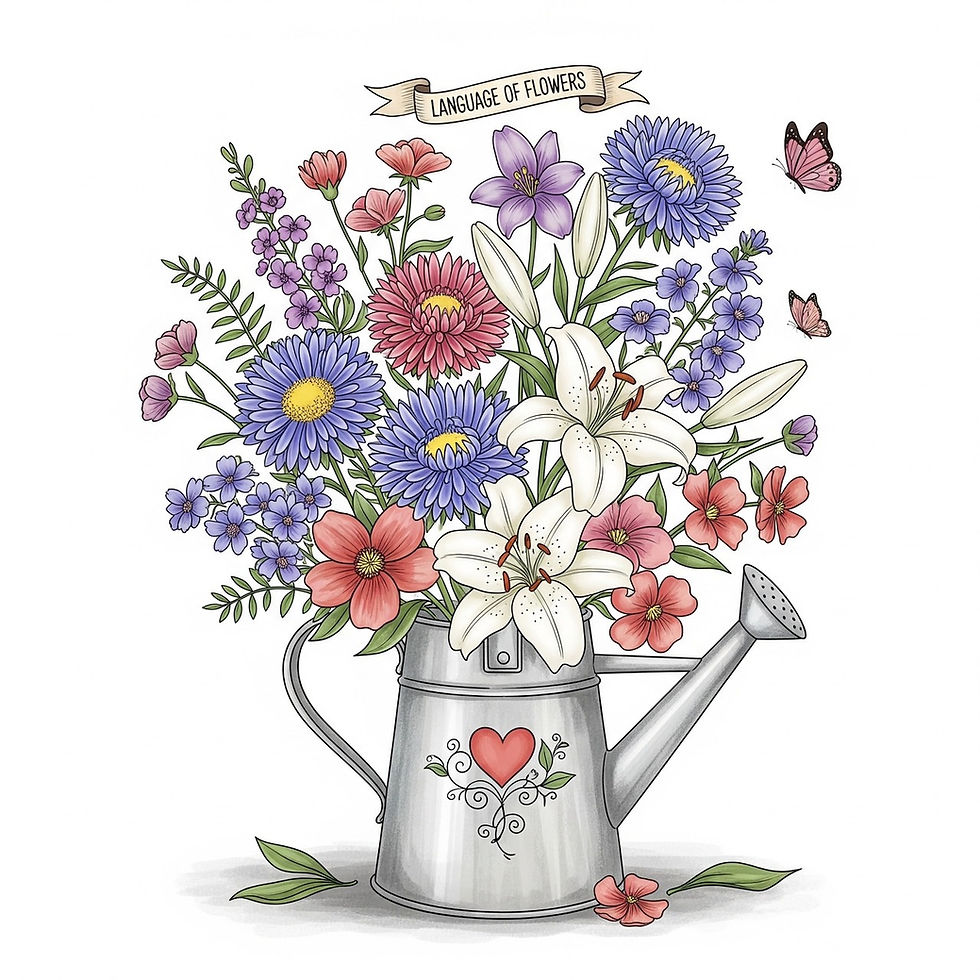

コメント