お盆に墓参りにいく意味
- Kazushige Maeda
- 2025年7月15日
- 読了時間: 3分
毎年8月半ばになると多くの人が故郷へ戻り、

家族とともにお墓参りを行うお盆。
日本の伝統行事のひとつでありながら、その由来や意味については意外と知られていないことも多いものです。
「お盆の由来」「墓参りに行く意味」「供養花のタブー」の3つの観点から、
お盆に込められた思いを見つめ直してみましょう。
1. お盆の由来は?
お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といいます。
これは仏教に由来する行事で、
古代インドのサンスクリット語「ウラバンナ」(倒懸=逆さ吊りの苦しみ)を
漢字で音写したものです。
仏教の教えでは、釈迦の弟子・目連尊者(もくれんそんじゃ)が、
亡き母が地獄で苦しんでいるのを知り、
供養を行ったことで母を救ったとされています。
この逸話から、「お盆」は祖先の霊を供養し、
感謝を伝える期間とされるようになりました。
日本では、仏教と先祖崇拝が融合するかたちで平安時代には広まり、
江戸時代には庶民の間でも一般的な年中行事となっていきました。
2. 墓参りにいく意味は?
お盆期間中(一般的には8月13日~16日)、
多くの家庭では「迎え火」を焚いて祖先の霊を迎え、
「送り火」で再びあの世へ見送ります。
その中で墓参りは、ご先祖様に直接会いに行き、
感謝の気持ちを伝える大切な行為とされています。
墓を清掃し、花や線香を供え、手を合わせることには、ご先祖様を忘れず、
私まで命が繋がっていることへの感謝を行う、という意味があります。
また、家族で行うことで、血とは、ご先祖さまとは、先人を敬うこととは何かなど、
大切なことを教え受け継ぐ教育的な役割も担っています。
墓参りは形式だけでなく、「今、自分があるのは先祖のおかげ」という原点に立ち返る時間でもあります。
3. 持っていくお墓や仏壇のお花のタブーは?
墓参りには季節の花を供えるのが一般的ですが、
供養にふさわしくないとされる花もあります。以下のような点に注意しましょう。
● トゲのある花(バラ、アザミなど)
トゲは「苦しみ」や「争い」を連想させるため、お供えには不向きとされています。
● 毒を持つ花(彼岸花など)
彼岸花は美しい花ですが、毒性があるため供養の場にはふさわしくないとされがちです。
● 強い香りの花(ユリ、クチナシなど)
匂いが強すぎる花は他の供物の香りを打ち消す場合があり、控えるのが無難です。
おすすめなのは、菊、リンドウ、トルコキキョウ、カーネーションなどの清らかで長持ちする花です。色合いは白を基調に、紫や淡い色を加えると、落ち着いた印象になります。
おわりに
お盆は、ご先祖様を敬い、今を生きる自分たちのルーツに感謝を捧げる大切な行事です。形式にとらわれすぎず、自分なりの気持ちで手を合わせることが何よりの供養になるでしょう。今年のお盆は、家族で墓参りに行き、静かな時間の中でご先祖様とのつながりを感じてみてはいかがでしょうか。


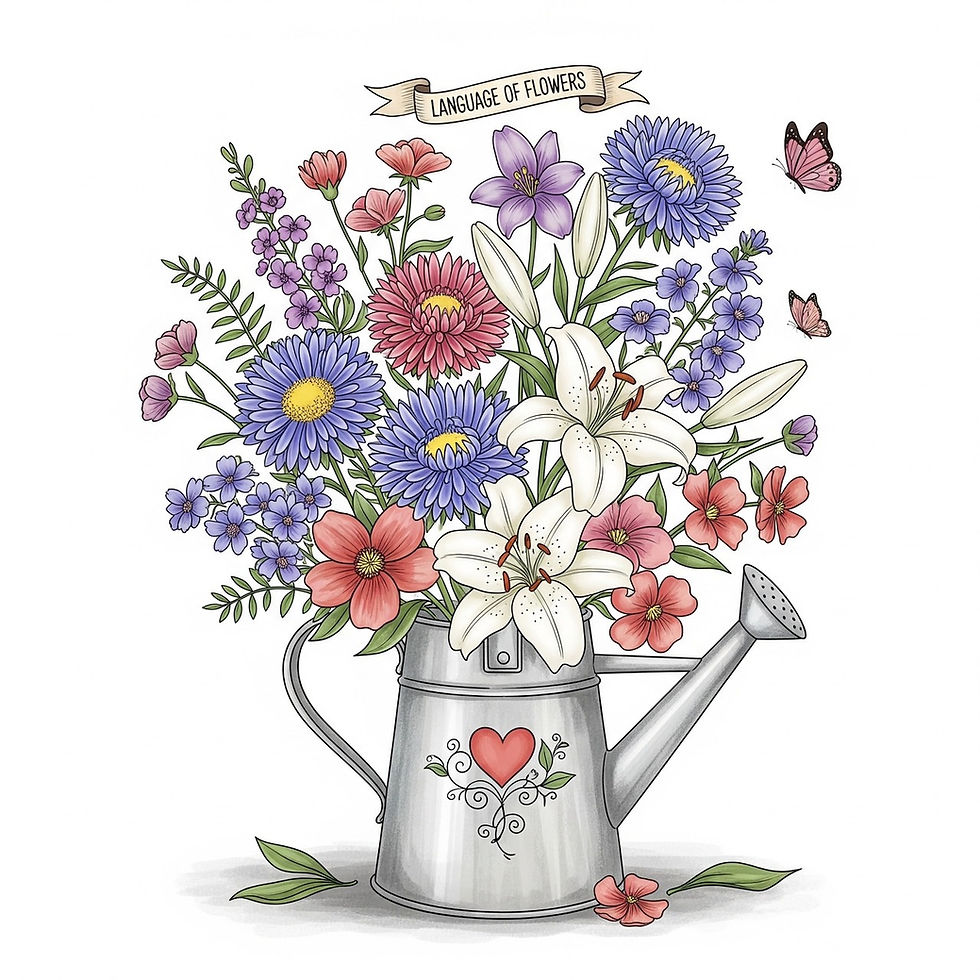

コメント